鵜戸神宮(宮崎県日南市)に行ってみた!!


こちらの観光スポットには2016年に訪れました。
車中泊の旅をする時は子どもたちを飽きさせない為に様々な観光スポットや家族湯などに立ち寄るようにしています。
それでは今回はそんな中から【宇都神宮】をご紹介していきます。
詳細データ

どこにある観光スポット?
鵜戸神宮(うどじんぐう)は、宮崎県日南市にある神社。
旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社に指定されている。
日向灘に面した断崖の中腹、東西38m、南北29m、高さ8.5mの岩窟(海食洞)内に本殿が鎮座。
参拝するには崖にそって作られた石段を降りる必要があり、神社としては珍しい「下り宮」のかたちとなっている。
この段が結構長いので足腰弱い人は注意して下さい。
病気もちの僕と長女はこれに泣かされました(笑)
住所・電話番号・駐車場情報


電話番号:0987-29-1001
営業時間:6時00分~18時00分
定休日:
駐車場:アリ・無料
観光ポイント




亀石…本殿前にある霊石で、豊玉姫が海神宮(わたつみのみや)から来訪する際に乗った亀が石と化したものと伝える。
石頂に枡形の穴が開くことから「枡形岩」とも呼ばれ、その穴に男性は左手、女性は右手で願いを込めた「運玉」を投げ入れることで願いがかなうといわれている。
かつては貨幣を投げ入れる風習であったが、1952(昭和27)年頃、落ちたお金を求め崖を降り磯に出る子がいて問題になった。
このため、賽銭に替わるものをと鵜戸小学校・鵜戸神官ともに試行錯誤した結果、1954年(昭和29年)から鵜戸小学校の児童らによって作られる、粘土を丸め運の文字を押した素焼きの「運玉」が使われることとなった。

男性は左手で、女性は右手で投げて下さい。
結構距離があるので難しいですが、なかなか楽しいですよ!!
観光ポイントの歴史




平安時代以来、海中に聳える奇岩怪礁とも相俟って修験道の一大道場として「西の高野」とも呼ばれる両部神道の霊地として栄えた。
中世以後、伊東氏の崇敬を受け1560年に伊東義祐によって社殿が再興された。
江戸時代初期の1631年には飫肥藩主伊東祐慶による造替、1641年にも同藩主伊東祐久による修復が行われた。
その後も1711年に同藩主伊東祐実による造替が、1770年に修復が行われた。
1868年の神仏判然令によって別当寺院の仁王護国寺を廃し、1874年に「神宮号」が宣下されるとともに官幣小社に列した。
1889年に社殿を改修、1895年に官幣大社に昇格し、第二次世界大戦後は神社本庁の別表神社となっている
1965年、NHKの朝の連続テレビ小説『たまゆら』の舞台に宮崎が選ばれたことも手伝って、昭和40年代には新婚旅行の定番地となった。
1968年に本殿及び末社を修復したが、翌々1970年、文政年間(1818~30年)に建てられた茅葺書院造の社務所を原因不明の火災により焼失し、それとともに古文書類の大半を失った。
1997年(平成9年)に屋根の葺き替えと漆の塗り替えを施したのが現在の社殿である。
アクセス情報

宮崎県の最南端に近い地域ということで宮崎市内からでも車で1時間と時間がかかる。
ただ、日南方面に高速道路の開発が進んでいるので今後に期待したい。
近隣に道の駅なんごうや酒谷があるので、道の駅めぐりをしている方は併せて立ち寄ってみるといいかもしれない。
周辺の道の駅情報

フェニックス
なんごう
酒谷
九州地方と宮崎県のSA/道の駅
 |  |
↑↑↑それぞれ画像クリックで進みます。
道の駅情報のほかに温泉や旅記事などもこのカテゴリーから読むことができます。
まとめ



今回の記事はここまでです、読んで頂きありがとうございました。
さて、当サイトでは同地方や他地域の様々な車中泊スポットや観光情報・温泉体験記などを九州地方を中心に発信しています。
以下のリンクから読むことができますのでどうぞ併せてご覧下さい。
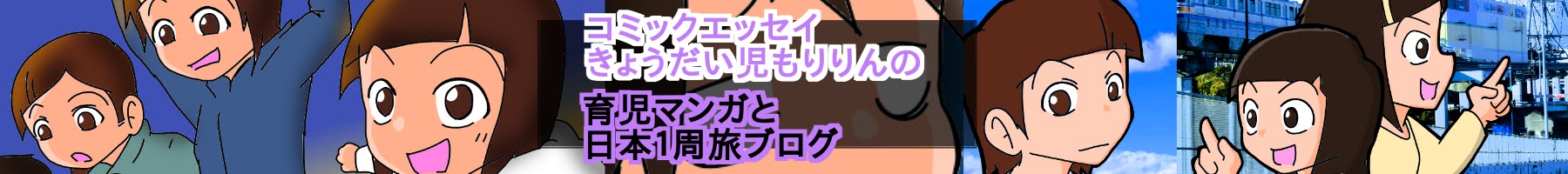
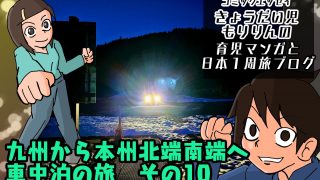





























コメント